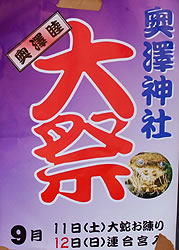* 旧奥沢村と奥沢神社について *
世田谷は大きな起伏はないものの、小さな起伏が多くあり、沢や丘が多い土地柄です。江戸時代にはこのような地形を世田谷七沢と称すことがありました。七沢は「北沢」「池沢(池尻)」「馬引沢(上馬、下馬)」「野沢」「廻沢(千歳台)」「深沢」「奥沢」を差していると言われています。
奥沢はそういった沢が多い地形の一番奥にあるという理由から奥沢と付けられたのではないかと推測されていますが、地名の由来に関してははっきりしないようです。

奥沢村が開けたのは伝承によると室町時代からです。建保元年(1213年)に鎌倉幕府の御家人、和田義盛が反乱を起し、打ち首になっていますが、その孫にあたる朝盛から8代目の朝清が家臣12名と共に奥沢に来て定住したという話が奥沢に住む和田家に伝わっています。
15世紀後半になると世田谷城の吉良氏の支配が及ぶようになり、家臣の大平出羽守が現在の九品仏浄真寺に奥沢城を築き、この地を治めます。現在でも現在鐘楼から下品堂の裏にかけて、土塁が残っているのを見る事ができます。築城年代に関しては天文20年(1551年)に吉良頼康から大平清九郎にこの付近の地を領地とする文章が存在するので、それ以前(14世紀頃)からあったかも・・・とされています。

廃城となったのは世田谷城と同じで天正18年(1590年)に豊臣秀吉の小田原遠征によって北条氏が滅亡した時です。その際に吉良氏は世田谷から逃げ出し、支城であった奥沢城も放棄されました。1658年には村が広くなりすぎたのか、村内で対立があったのか分かりませんが、奥沢村から分裂して新たに奥沢新田村が生まれます。現在でいう奥沢4~8丁目辺りです。
そしてそれを契機に1670年頃から荒れ放題となっていた奥沢城跡地を利用して九品仏浄真寺が建てられていき、奥沢は小さな門前町としても発展することになります。奥沢新田の開村に伴って檀那寺が必要だった村と、ちょうどこの時期に寺地を欲していた珂碩上人と、そして大きな寺を興すのに都合よく城跡という広い場所があったという思惑や偶然が重なったようです。

時代が明治になり、明治9年には本村と新田村が合併し、再び一つの奥沢村となります。明治21年の調べでは総戸数162戸、833人が暮らしていたようです。大正12年には目蒲線が開通し、更には関東大震災が起き、宅地化が進んでいきます。奥沢では他の玉川地域で行われた玉川全円耕地整理に先駆けて一部民間によって宅地開発が行われました。
この区画には海軍軍人が集団で住んでいたので、海軍村と呼ばれることになります。奥沢に海軍村といってもピンときませんが、奥沢の立地がちょうど基地のある横須賀と司令部のある都心との中間というか、鉄道が敷かれたことでどちらにも行きやすかった事と、まだ土地が安かった事、それから海軍自体が集団生活を好んだことで多くの軍人が移住してきました。
現在でもこの地域は他の地区よりも道が狭く、昔の名残と留めた家があったりします。昭和2年には大井町線、東横線が開通し、交通の便が飛躍的に向上します。それに伴い耕地整理がどんどんと行われていき、宅地率95.1%という世田谷区内でも屈指の住宅地域となっていきます。

奥沢は本村と新田村とがあったので、2つの鎮守がありました。本村の鎮守だったのが子安稲荷神社で、創建年代や由緒などは不明なようです。新田村の鎮守は八幡神社で、吉良氏の家臣の大平氏が奥沢城を築いた際に守護神として八幡神社を勧請したと伝えられています。
明治になって村が合併し、合祀令もあり、明治42年に八幡神社に子安稲荷社を合祀するといった形で奥沢神社が誕生しました。そのため、祭神は八幡社の誉田別命(別名応神天皇)、稲荷社の倉稲魂命の2柱です。新編武蔵風土記稿によると八幡社は本社3間半に1間、拝殿2間に3間。前に鳥居が建てられていて、本社の右には4間に2間の寮があって神社を管理する人が住んでいたとあります。

この本社は明治45年に新しい本殿が再建された時に九品仏浄真寺に譲られ、現在でも改修され観音堂として使われています。そして寮の方は、慶応末からこの寮で土地の子弟を集めて読、書、算を教えるようになり、明治12年には一部を改修して認可を得て、社名をとって「八幡小学校」としました。これが現在の八幡小学校の基礎であり、現在の社務所のところに「八幡小学校発祥之地」の碑が建てられています。

昭和3年にはそれまであった宮島の海中の鳥居と同じ形だった木の鳥居から石の鳥居に建て替えました。昭和45年には社殿の建替えを行っています。新しい社殿は尾州檜材を用い、室町期の様式を採用したもので、都内においても他に類を見ないものとなっています。
建替え以前の旧社殿はやはり同じように九品仏浄真寺に譲られ、五社様として祀られています。特に九品仏と深い関係があるわけではなく、単に置き場がなかったからだと言われています。
また本殿の左奥には弁才天女が祀られています。これはかつて奥沢駅の少し南にあった湧水池、奥沢弁天池に鎮座していたものを昭和25年に移したものです。岩が積み上げられてちょっと大袈裟な感じになっていますが、昭和47年に築山造園を行って現在の状態にしたそうです。