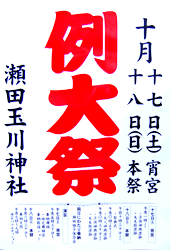* 旧瀬田村と玉川と瀬田玉川神社について *
瀬田と言えば国道246号と環八が交わる瀬田交差点が有名かと思います。その瀬田交差点を下っていくと二子玉川に至り、逆の方向に進むと用賀に至り、田園都市線で言うなら用賀と二子玉川の間にある町域といった認識かと思います。
現在では瀬田と聞いてもあまりパッとした印象がありませんが、瀬田の歴史は古く、地名は奈良時代から平安初期に書かれた倭名抄に多磨郡勢多郷と記されているほどです。しかもその頃は少なくとも用賀を含むもっと広い地域を示していたのではと考えられています。

ちなみに世田谷という地名は永和2年(1376年)に「世田谷郷」と記されているのが一番古いようですが、この地名の由来には諸説あって、その中の一つにこの瀬田の地名から「勢多(瀬田)の谷地」となり、世田ヶ谷になったといった説もあるようです。
ただこれはどちらかというと少数意見で、狭小な海峡の意味の「瀬戸」が、海に関係なく狭い谷地も「瀬戸」と呼ばれるようになり、台地の間の狭い小谷の意味で「せとがや(瀬戸ヶ谷)」がなまったのではといった説の方が有力みたいですが、すぐ隣の村(昔は用賀が瀬田村、桜新町や桜丘が世田谷村)という事を考えると何かしらの関係があってもおかしくないように思います。

正式に瀬田と書かれるようになったのは14世紀ごろです。足利氏満の書簡に荏原郡瀬田郷とあります。その頃の瀬田村も今よりも広大な村域を誇っていました。現在の二子玉川周辺の玉川1~4丁目は昭和7年に世田谷区が成立した際に玉川町として分離したものです。また世田谷通りに三本杉陸橋がありますが、この付近から砧公園にかけても瀬田村三本杉という地域だったものを昭和43~46年の町域変更の際に大蔵一丁目に移したものです。玉川台という町域も同じ時期に瀬田と用賀から町域を分けて新しく造られた町域なので、環八付近の玉川台も瀬田の町域でした。
更には古い地図を見ると、多摩川の向こう岸に瀬田村の文字があります。多摩川の流路変更で取り残された土地で、この土地は明治45年に神奈川県に移され、逆に玉川一丁目の東部分はその時に神奈川から移ってきた部分です。昔の瀬田の低地にはあちこち沼地があったそうです。それは川の流れが変って取り残された跡で、多摩川の洪水によって度々流路変更が行われ、境界も何度となく変っていたようです。

このように瀬田という土地はかつては大きな村域を持つ村でした。瀬田が発展した理由は鎌倉時代になると鎌倉を中心とした鎌倉道が整備され、その主要な3本の道の真ん中の中の道が二子を通っていたとされている事が上げられます。伝説ですが、兵庫島は新田義興が足利氏のだまし討ちに遭って自害した地とされています。
永禄年間(1558~69年)には北条氏の直臣長崎伊予守重光とその子重高がこの瀬田の地を賜って居を移し、瀬田城を築いたとされています。行善寺の近く、ゴルフ練習場の付近がその跡地とされていますが、昔の遺構は全く残っていません。同じ時期にやってきた北条氏の家臣、南条氏が深沢に造った兎々呂城は簡単な土塁で囲った城だった事を考えると、そういった類の小規模なものだったに違いありません。それでも立地的には守るに易く、攻めるに難しい城址だったと言われています。

長崎氏は北条氏の滅亡後にはこの地に留まり、瀬田の地主として帰農します。岡本にある民家園に展示してある古民家は長崎家のものを瀬田から移築したものです。江戸時代になると街道が整備され、大山道の二子の渡しの利用者も多くなります。
ただこの時代は、いわゆる崖下の土地、現在の玉川地域には住む人は少なく、田んぼが広がる田園地帯で、瀬田原、瀬田耕地などと呼ばれていました。渡しの場所には旅館や茶屋が並んでいるようなイメージを描いてしまいますが、川向こうの溝ノ口村や二子村の方が宿場となっていたようで、瀬田村には宿がなく、幕末にようやく一軒宿ができたとのことです。
その代わりというか、天保年間の記録では茶屋が7、8軒川原の堤にあったようです。洪水が多い土地だったので、崖上に住居が多かったのも頷けます。行善寺も洪水によって現在の見晴らしのいい高台に移ってきたといわれています。

瀬田村が急速に発展していくのは明治40年に玉電が開通してからです。同じ頃に多摩川改修工事も行われ、河畔には料亭が並び、多摩川には屋形船が浮かんで新鮮な鮎料理が出されていました。更には玉川遊園地も造られ、多摩川沿いの低地が次第に郊外行楽地となっていきます。
大正時代になると丘陵地帯には著名人の別荘も並ぶようになり、大きな歓楽街として玉川地域が発展していきました。今でもその面白い名残があり、行善寺には猫塚があるのですが、これは歓楽街で使われた三味線の材料となった猫を供養した塚です。元々は歓楽街にあったそうですが、こちらの境内に移されました。また慈眼寺の近くには瘡守稲荷神社がありますが、「瘡」には「おでき」などの悪いもの、或いは梅毒(性病)の意味もあるので芸者さんたちの信仰も厚かったそうです。

行政的には明治から昭和初期にかけて色々と起こります。明治11年には用賀村と連合村を形成し、瀬田用賀連合村となり、明治22年には戸数が少なくて税収の少ない村は合併するように政府から促され、周辺の等々力や野毛などといった村と合併し、玉川村の一部となります。
この合併に関してはかなり揉めました。どこに役場を置くのか、村名は、どこの村とは一緒になりたくない、などなど。瀬田村(瀬田、用賀、野良田、上野毛)、等々力村(等々力、尾山、奥沢、野毛)といった2村案も出されていたそうです。玉川村の名前は明治8年に等々力に開校した玉川学校の玉川を、妥協の産物として付けたものです。こんな状態なので、玉川村が成立した後も村内の対立は絶えず、村長職が空いたり、村外の人間に村長を頼んだこともあったそうです。
昭和7年には世田谷区が成立し、玉川村は世田谷区に編入します。その際に瀬田村は丸子川を境界に崖上の玉川瀬田町と崖下の玉川町に分かれます。戦後、昭和22年に板橋区から練馬区が独立し、東京が23区に増えました。同じ時期に玉川区独立案が区議会に持ち込まれましたが、後の不況で立ち消えとなってしまったのはあまり知られていない事かもしれません。玉川全円耕地整理の際にも脅迫やらボイコットやら様々な騒動が起きていますし、何かとよく揉める地域ともいえるかもしれません。

瀬田交差点の北側、いわゆる昔の大山道の慈眼寺ルート沿いの崖地に瀬田村の村社であった瀬田玉川神社があります。元々は御嶽神社で、明治18年に役所に提出した書類の由緒には、「戦国時代の永禄年間(1558~70年)に、この村の下屋敷に勧請し、その後、寛永三年(1626年)、瀧ヶ谷に長崎四郎右衛門嘉国が寄付をして遷宮した」と書かれているようです。
また、神社に現存する棟札には、元禄八年(1695年)、長崎四郎左衛門嘉満、又四郎嘉包が、子孫の長久繁栄を祈願して、拝殿一宇(棟)を造営したと記録されているそうです。初代の別当は、真言宗慈眼寺権大僧都源長で、代々別当として慈眼寺が管理してきました。明治7年には村社に定められ、同41年には合祀令によって村内にあった八幡社、熊野神社、天祖神社、六所宮などを合祀し、社号を村名より玉川神社と改称しました。

この玉川神社の名称が色々と物事を複雑にしているように感じます。確かに当時は玉川村瀬田だったので玉川神社というのもありかと思いますが、合祀してその地名、例えばお隣の用賀のように用賀神社と付けることはあっても地域全体の名を付けることは一般的ではないように感じます。
同じ年には等々力でも合祀によって玉川神社が誕生しています。等々力の方は役場が置かれるなど玉川村の中心的な存在でしたが、瀬田の方は元々用賀などと瀬田村を画策していた経緯を考えると、我々の神社こそが玉川村で一番の神社といった思いが入っているのかもしれません。

更に悪いことに、後に世田谷区が成立した際に玉川村が消滅した代わりに、瀬田の平地部分が玉川町として独立しました。玉川村の玉川のつもりが、玉川町ができてしまったら瀬田地区の住民にしてみれば、玉川町の神社のような感じとなってしまいちょっと複雑です。
後に瀬田と玉川の両地区の氏神様として瀬田玉川神社と呼ばれることになります。等々力にある玉川神社は等々力の玉川神社という意味ですが、瀬田玉川神社は瀬田にある玉川神社、瀬田にある瀬田と玉川の両地区の神社、いわゆる瀬田玉川神社と二通りの解釈ができるわけで、このへんは色々と揉める原因になるので氏子の間では曖昧になっているような感じでした。

瀬田玉川神社は古墳の上に建てられています。大正3年に社殿を改築し、同12年には関東大震災の被害を受けて補修が行われました。境内には遠くからも見ることができた樹齢7~800年の黒松があり、神社のシンボルになっていましたが、昭和41年の台風で惜しくも折れてしまいました。今ではその幹が御神木として祀られています。現在の社殿や社務所は昭和43年(1968年)に再建されたものです。