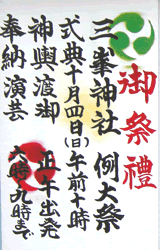* 砧と砧三峯神社について *
環八が右辺、小田急線が上辺、仙川が左辺、そして世田谷通り(一部旧道)が底辺といった方形に近い町域を持っているのが砧です。砧と聞くとまず砧公園を思い浮かべる人もいるかと思いますが、砧公園はこの町域ではなく、もっと南側にあります。
現在の砧は通りや線路に囲まれた不自然な形をしている町域で、かつては大蔵村の一部でした。最初に砧の名が登場するのは明治22年の事。多摩川流域付近にある大蔵、鎌田、岡本、喜多見、宇奈根の5村が合併し、そのときに生まれたのが砧村です。ちょうど小田急線から北側の村が合併して千歳村ができたのと一緒です。
千歳村の場合には村民に投票で縁起のいい千歳の名が付けられたのですが、砧の場合はこの地域に根付いた名前が付けられました。砧という言葉は、世田谷区の見解を見ると、「古く7、8世紀のころ、朝廷に納める布を衣板(きぬいた)でたたいて柔らかくし、つやを出すために使った道具から生まれたといわれています。女の人の夜なべ仕事として砧の音が響いたことや、その布を染め、多摩川の清流にさらして洗ったことなどは詩情にもうたわれてきました。」との事です。同じく多摩川沿いにある調布とか布田、染地などと通じるものがあります。

その大規模な村連合の砧村は昭和11年に世田谷区に属する事となり、世田谷区大蔵といった元々の所属していた村の住所表記になりました。この時に砧の名はいったん消滅します。昭和30年になると複雑に絡み合った旧大蔵村、旧鎌田村地域の飛び地が整理され、この2村の細長い地形が、北が砧、真ん中が大蔵、南が鎌田といった具合に分けられました。概ね旧大蔵村の山野地域が新たな町域である砧になったといった感じです。
この山野地域は真ん中を流れる谷戸川で西と東に分かれ、川周辺に田んぼが開け、農家が点在しているといった地域でした。そして東側、現在の環八付近は世田谷でもっとも標高が高い地点で、その場所には山野給水場(現、砧給水場)が建てられていました。とりわけこの給水所の周辺は雑木林が広がり、開発が遅かった地域です。この地域は多摩川から遠く、土地も高台の台地にあるので、町名の由来となった砧が使われていたかは怪しいかもしれません。

昭和35~42年にかけて環八と世田谷通りが整備され、現在の町域が決まります。その後急速に宅地化が進み、田畑が消え、雑木林が消えていきました。現在大蔵山野地区だった痕跡は余りありませんが、山野小学校や山野公園などにその名が受け継がれています。
砧は新しくできた町なので、特に何もないと言えば何もない地域なのですが、新しい町だからこその特徴もあります。それは撮影所が多い町なのです。東宝の砧撮影所、ウルトラマンで知られる円谷プロダクション、NHKの放送技術研究所、TMC(東京メディアシティ)といった撮影所があります。円谷プロは移転してしまいましたが、こういった撮影所が近いという立地上、成城に並んで著名人が多く暮らしている町でもあります。

砧の氏神は三峯神社です。神社について少し知識のある人はあれっと感じるかもしれません。多くの場合、三峯神社は境内社とか、町の路地にひっそりとある小さな祠として存在しているからです。三峯神社は秩父の三峯山に鎮座する山岳信仰の秩父神社を本社とする神社で、祭神は国生みの神、伊弉諾尊と伊弉册尊です。
三峯神社と言えば三峯講です。江戸時代中期から後期にかけて秩父の山中に棲息する狼を猪などから農作物を守る「お犬さま」として崇める御眷属(ごけんぞく)信仰が流行るようになります。さらに、この狼が盗戝や災難から守る神と解釈されるようになると、関東・東北等を中心に江戸の町や農村集落でも信仰されるようになり、各地から三峯山へ参拝する三峯講(三峰代参講)が行われました。砧でもこの頃より三峯講が行われていて、宝暦(1751~63)、安政(1854~59)、文久(1861~63)の年号が入った三峯神社発行の代参帖・寄付金額収書等が残っています。

とまあ古くから砧では三峯講が行われていたのですが、講はあくまでも講であって、氏神とは違います。一般に村では神社の氏子、寺の檀家といった組織が主であって、講は副の組織になります。例えば世田谷では大山講も知られていますが、それは雨が降らなく困った場合とかに行われるもので、日常の氏神だけではどうにもならない場合のプラスアルファ的な意味合いであり、あくまでも村の外の神様です。いってみれば氏子などの切れない関係ではなく、利害関係で結ばれた関係と簡潔にいう方がわかりやすいかもしれません。
だから先に書いたように三峯神社は地域の氏神様を越えることはなく、境内社とか、街角の小さな祠で存在するのが普通であって、このような立派な社殿があり、村の鎮守として存在しているのは珍しいのです。

その理由は、砧町が新しくできた町だからです。それまでは大蔵村山野だったので、氏神は大蔵村本村の氷川神社でした。砧から本村までは結構距離がありましたが、一村一社の合祀令があったし、人口が多いわけでもなかったので神社が造れずにいました。
戦後になると合祀令が解け、宅地化が進んで人口が増え、昭和27年に大蔵氷川神社の氏子から離れて、三峯講の蚕様として祀られていた三峯神社を砧地域の氏神とすることに決めました。この地域は日当たりのいい丘があったので桑畑がたくさんあり、古くから養蚕が盛んだったという土地柄だったので、三峯講が盛んだったのです。それに隣町にあたる横根稲荷神社や宇山稲荷神社が合祀先から独立した影響もあったことでしょう。それまでは37坪という小さな境内だったのを350坪に広げ、昭和37年には社殿、拝殿を新築し、神社の形態が整えられます。この時に秩父三峯神社から分霊を勧請して安置しています。

昭和46年には正式に神社の指定を受け、昭和48年に社務所、昭和52年に手水舎、昭和59年に灯籠、平成元年に神輿、平成二年に舞台兼御輿舎が建設されるなど、神社の陣容が少しずつ整えられていきます。新しい神社なので境内には特に古いものがありませんが、三峯信仰の象徴である狼の像は社殿前にあるのが大正時代のもの。手水舎近くにあるものが昭和初期と神社として整備される前のものです。この他、境内には稲荷神社が境内社として祀られています。