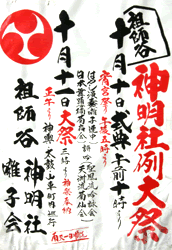祖師谷神明社の神輿渡御は本祭の日曜日に行われます。年によって違うかもしれませんが、12時頃に出発式が始まり、その後宮出しが行われ、19時頃に神社に戻ってきます。ここの神輿渡御は古式の独特なスタイルが踏襲されていてとても興味深いです。
まず最初に行われる式典ですが、これは他と一緒なのですが、御神酒を飲んで式典が終了するまで神輿は御輿舎の中です。式典が終わると初めて社殿の前に運び、用意ができ次第出発します。こういった手順はそれぞれなのでしょうが、神輿の前で行うのが一般的で、区内では他にないスタイルかと思います。
神輿への御霊入れは前日の祭事が行われた後に行われます。これも厳粛に鯨幕を使用し、御霊を運ぶといったものです。社殿から御輿舎まで少し距離があるので、宮司さんは鯨幕に囲まれ少し歩かなければなりません。

神輿渡御にあたっては、黒の烏帽子に白丁装束姿の神輿を警護する輿守が付きます。彼らは烏帽子の上から手ぬぐいを鉢巻きのように巻き、白丁装束の背中には「神」の大きな字が染め抜かれ、手には大黒様と福の字が描かれている赤い団扇を持っているといった独特のスタイルです。これは古くからの風習のようで、熊野神社と交互に祭礼を行っていたときからこういった風習があったみたいです。
実際のところ警護するといっても、混雑する最後の商店街ぐらいしか役目がないので、先頭で弊を持った人以外は宮出しや道中はぞろぞろと神輿の後ろを歩いていたりします。ここに限らず世田谷の神輿渡御はどこでものんびりとしたものなので、神輿を見守りながら散歩といった感じでお年寄りの方々は楽しそうでした。

神輿は戦前の昭和3年に浅草の平川商店で製作されたもので、延軒屋根の勾欄造り、台座の長さは二尺四寸(80cm)です。神輿の巡行経路は駅から続く商店街通りを中心に祖師谷1丁目から6丁目、そして昭和45年頃まで祖師谷の町域だった成城7~9丁目の7丁目を中心に回るようになっています。
祖師谷には驚くことに大通りがありません。環八横断といったような事は夢のまた夢。2車線道路すらなかなか見かけない地域なのです。ひたすら狭い道を進むので、渡御のハイライトはウルトラマンの立像がある祖師ヶ谷大蔵駅前とか、駅前から続く商店街となります。
駅前の広場では最後の休憩が行われ、その時に囃子が演奏され、観客を魅了します。そして観客のテンションが上がったところで神輿が祖師谷通りのウルトラマン商店街を進んでいきます。地元の商店街なので歓声も多く、狭い通りなので観客との距離も近く、担ぎ手のテンションも上がりますが、それに輪をかけているのが「おひねり」を神輿に投げるといった変わった風習です。

おひねりを神輿に投げると言った風習は、見慣れていないととても奇妙な習慣に感じます。おひねりとはお金を白い紙で包んだもので、よく舞台に投げ込まれるやつです。そもそも神輿にものを投げたら罰が当たるし、お金を投げてもいいの?なんて思ったりする人も多いのではないでしょうか。
神輿におひねりを投げるといった風習は、世田谷ではここだけですが、全国的にみると珍しいというわけではありません。お賽銭を投げると言った行為の延長上と考えれば納得できるのではないでしょうか。ただ祖師谷の場合は全国的にみてもその規模が大きく、ちゃんと調べていませんがここまで派手に行われているのは他にないかもしれません。

祖師谷のおひねりは商店街で行われます。宮入前に最後の休憩を駅前の広場で行いますが、その前からおひねりが飛んでくるようになります。おひねりを投げるのは商店街の店の人がほとんどで、白い紙に包んだおひねりをお盆や籠に載せて店の前でお神輿がやってくるのを待ち、神輿がやってくると屋根にめがけて投げるといったものです。
神輿の少し前を歩く警護の人たちがおひねりの盆を持った店の前で提灯を上げて神輿を誘導します。沢山おひねりが飛んでくると神輿の向きを変えて神輿を揺らしたりもします。こういった事が長い商店街の渡御中にずっと続くので、とても賑やかな渡御になります。担ぎ手にしてもお神輿がくるのを待ってくれている人がいて、おひねりが飛び交う中を渡御するのは楽しいものです。

ただ担ぎ手にとっては楽しいだけではなく、ちょっと問題もあります。紙で巻いているとはいえ、やっぱり金属で出来たお金です。大量に振ってくれば痛いですし、遠くから勢いよく投げられると溜まりません。投げる方もなるべく屋根に載せるような感じで投げていますが、勢い余って反対側に飛んでいってしまうこともあったりと、運が悪いとたんこぶが出来てしまうそうです。
おひねりは屋根にのっかることもありますが、ほとんどは地面に落ちてしまいます。落ちたものは後ろを歩いている関係者が拾っていきます。聞くと、一般の人も拾っていいそうです。多くのおひねりを用意するのも大変そうですが、それを拾って回収するのもまた重労働のようで、年配の関係者が腰が痛そうに拾っていました。

なぜこういった風習があるのか。気になって聞いてみたのですが、ここの関係者にとっては古くから当り前に行われてきたことなので、あまり深く意識したことはないといった感じでした。始まりはどうだったのか分からないけど、商店街の付き合いでこういった風習が大きくなっていったようです。実際に見学するまでは何でこういった文化があるのだろうと疑問だったのですが、行われている様子を見るとその理由は何となく理解できました。店の前などで投げている人がとても楽しそうだったからです。
夏には各地で神輿に水をかける水掛祭りとか、温泉地ではお湯かけ祭りといったものがあります。ある意味それと同じです。実際にそういったものをかけることで、見ている側も祭りに参加している気になり、一体感が生まれます。古くからの商店街の付き合いといっていたのはその部分であり、自分の家族が担ぎ手、或いは輿守として参加していたり、商店街の仲間が頑張っているといった場合、神輿が通るときに盛り上げよう。担がない方も何かして盛り上げようといった事が根底にあり、このような派手なおひねりを投げるといった文化になっていたんだと思います。言うなればおひねりでの歓待といったところでしょうか。

全国的にこういった風習が流行らないのはおひねりを用意するのが大変ですし、拾って回収するのも大変です。実際のところ小さなお金を包んでいるのでそんなにお金がかかるわけではありません。手間がかかるだけです。千円を封筒に包んで渡してもらう方がよほど効率的です。それに担ぎ手が痛い思いをするので離れた場所からは投げられません。
祖師谷のように狭い商店街でないとなかなか出来ないことです。それにお金が溝に落ちてしまうような場所ではやりにくいだろうし、ましてや草むらがある場所ではもっと駄目です。そういった事を考えるとやはり回収する手間を考えると一般的にやりにくい行事で、境内のみで小規模に行われたりするのも納得で、ここが特殊なんだなと感じます。

長い、長い商店街でのおひねりの歓待が終わると、最後は宮入です。が、しかし、長い商店街の間ずっと担ぎっぱなしだし、店の前で揉んだりもするので、商店街が終わる頃には担ぎ手の脚がふらふらの状態です。途中で崩れることもあります。
宮入は宮出しと同じように参道を進みます。境内に入ると神輿を回します。ただでさえ足が立たない状態なので、すぐに崩れていました。そして最後に社殿前で収めます。あまりにもふらふらな状態だったからなのか、すぐに収めていました。神輿が降ろされるとすぐに御霊戻しの神事が行われ、鯨幕を利用し、御霊が本殿に戻されます。そして社殿内で神事が行われ神輿渡御と例大祭が終了します。